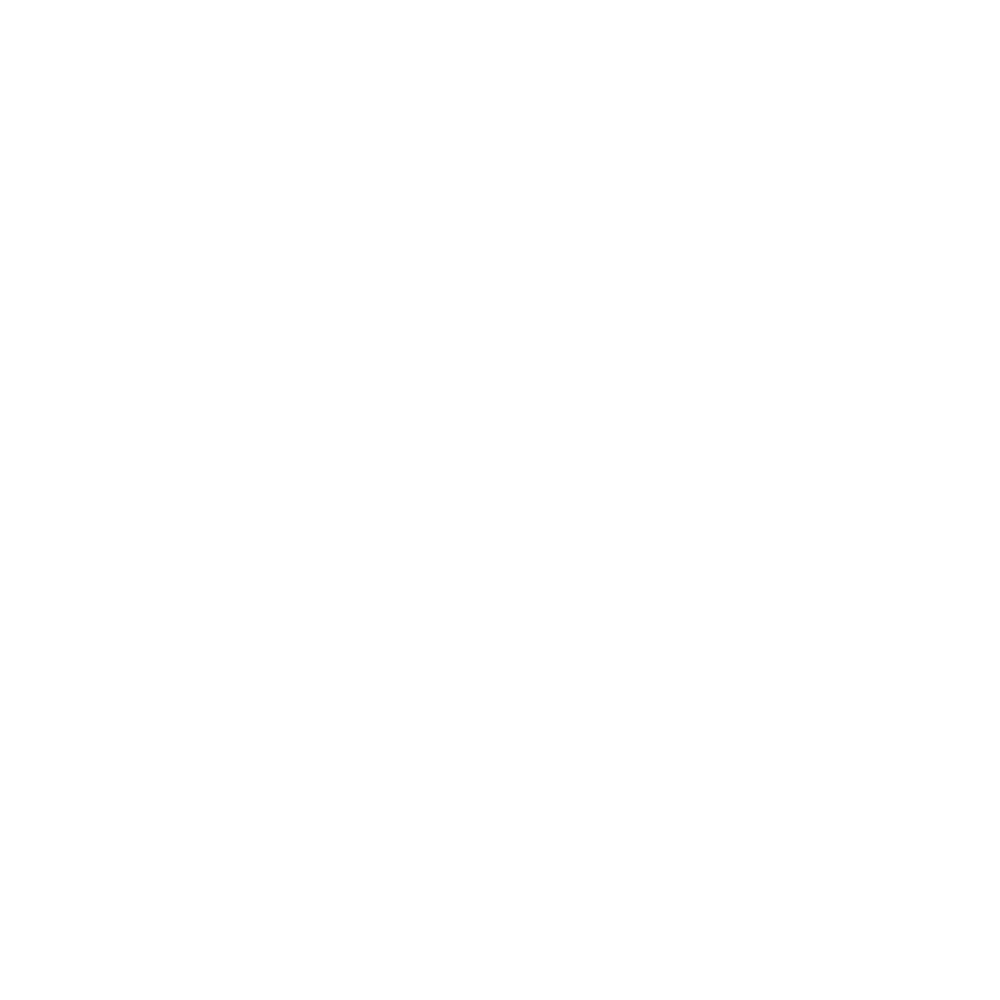Databaseのっぺらぼうと天宿りの牙卵 情報集
雑文
御題目一覧
※このページ内の記事には、本編のネタバレを多分に含みます。
前口上
『のっぺらぼうと天宿りの牙卵』の制作中、「本編では描写する機会がなさそうだけど、どこかで公開しておきたいな〜」と思ったネタなどについて、こちらにちらほら記載していこうかなと思っています。
本編に関するネタバレががんがん出てきますので、未読の方はご注意ください!
(できたら弐ノ下のラストまで読み終えてから、こちらの記事を読んでいただきたい気持ちです…!)
真面目なネタとしょうもないネタの落差が激しい感じになる気がしますが、好き勝手やっていきますので、ゆるーいお心持ちでお付き合いいただけたら幸いです。
『ラノベ夢幻能』の巻
弐ノ下刊行後からちょこちょこ宣伝文句に使い始めた、「ラノベ夢幻能」という造語について。
「夢幻能」っていうのはそもそも「能」の分類であって、「ラノベ」な時点で「能」ではないという即オチ2コマみたいな破綻した造語なんですけど、なんでそんな造語を使い始めたかっていう深そうで浅いゆるゆるな解説をしてみます。
そもそも『能』とは?
日本の伝統的な歌舞劇のこと。
奈良時代に大陸から渡来した散楽(曲芸や奇術)が変化して「猿楽」となり、平安鎌倉期にものまねや寸劇などの芸に変化。
これが鎌倉時代の終わりから南北朝時代にかけて更に変化していき、「能」や「狂言」になりました。
室町時代に観阿弥・世阿弥が体系化し、それを足利義満が熱烈支援したことで大きく発展しました。
(「犬王」をご覧の方にはイメージが付きやすいかもしれませんね!!)
『能』の特徴
これは大きくふたつあります。
・面をつけて演じること。
・主人公が主に人外(現世に未練のある死霊や、神・精霊など)であること。
この辺で、ちょっと「お???」と思われた方がいるかもしれません。
『能』と『狂言』の違い
先程、「猿楽」が「能」と「狂言」に変化したと書きましたが、実は今でも、「能楽」という言葉には能と狂言どちらも含まれています。
・能:主に死者が主人公で悲劇的、人間の苦しみや悲しみに視点を向ける芸
・狂言:主に生者が主人公で喜劇的、笑いや風刺を中心とした芸
人生には喜びもあれば苦しみもある、という二面性を、能楽では能と狂言で描いているそうです。
「狂言」についての話は、本項でお伝えしたかった内容からは少し話がそれてしまいました。
でも後日掲載予定の『和御魂』の項目で少し触れたい内容でもあったので、なんとなく覚えていていただけたら嬉しいです。
『夢幻能』とは
で、結局夢幻能とは何なのか。
能は大体2つの形式に分類されるのですが、その中でも、死霊や神、鬼、精霊などを描くのが「夢幻能」。(対:現代能)
超現実的存在である主人公が、僧侶などの旅人の前に姿を現して、土地にまつわる伝説や身の上を語る形式で物語が綴られます。
……ということを、実は『のっぺらぼうと天宿りの牙卵』の一作目を書いた時、私は知りませんでした。笑
ですが縁あって能の勉強をし始めた際、
「えっ…、己の死に気づかず、
しかし未練に繋がれて成仏できずに彷徨う死霊が…、
旅の法師に己の事情を語り…、
その助けを得て…成仏する……。
えっ、それ、牙卵じゃん…?」
などと思うに至りまして…。
(荒魂成仏しなかったけど)
(能でも、未練を拭えない魂は成仏できなかったりもする)
いや日本を代表する伝統芸能に対して、めちゃくちゃ厚顔無恥なこと言ってるなとは思うんですけども。
子供の頃から色々な物語に触れてきた中で、恐らく世阿弥の夢幻能をモチーフにした物語に出会った経験も、きっとあったのだろうと思います。
でも、自分が「和風ファンタジーを書いてみよう!」と思って綴った物語が、意図せず600年以上前からこの国で脈々と語り継がれてきた物語の形式を踏襲していた、ということに、なんだか運命のようなものを感じてしまって。
能の演目をいくつか学んだ上で、改めて、今度こそ「私なりの夢幻能」を執筆してみたいと思い、制作したのが「奥台・御晴野編」でした。
シテ(主役・死霊や神など超現実的存在)、ワキ(相手役・僧侶など)が明確だった一作目とは違い、「奥台・御晴野編」は刻雨・荒魂・結唄・韵貞をそれぞれシテとみなせるように配置し、それぞれの事情や思惑をかけあわせて展開させました。
そのため、正直一作目より「夢幻能」的な色合いはわかりにくくなったような気もします。
ですがその分、「前シテ・後シテ」を意識したシテの性質変化や、能だけでなく和歌の美的理念ともされる「幽玄」を現代風に表現するならどんな感じになるだろうか、というようなことを、私なりに諸々考えて噛み砕きながら、物語の要所要所に匂わせてみたりしました。
まあ結局は自己満足に過ぎないのですが、笑、そんな経緯があって、宣伝文句に『ラノベ夢幻能』なる造語を使ってみた次第です。
能、とっても奥深い芸能ですので、これを機会に興味を持っていただけたりしたら嬉しいです。
余談ですが、私も「奥台・御晴野編」を書き始めてから2度ほど舞台を見に行きました。いわゆるエンターテイメントとは全く違った空気を感じることができてとっても面白かったです。
でも、ごめんなさい、毎回途中で寝てしまうのだけど…。笑
能の曲調って、心臓の音に近い?のでα波が出るとか、瞑想に至りやすいとか、そんなふうにも言われているらしいです。
そうやって、夢か現か分からない状態で舞台を味わうのも、能の醍醐味なんだとか。(何をどう頑張ってもどうしても起きていられない私は、その言説に救われました。笑)
『煤払い』の巻
──そんな煤払い後の襤褸雑巾みてえな風体にされやがって。
──それにしたって、『煤払い後の襤褸雑巾』はひどいですよ。ふつうに悪口です。
現代では、やる気に満ち満ちているにせよ、致し方無しにせよ、都合の良い日に腹を決めて行う大掃除ですが、近世までは煤払い=大掃除は、12月13日に行うものだと決まっていたそうです。
理由は諸説あるようですが、ひとつには、12月13日が「正月事始め」「松迎え」の日であり、正月の準備を始める時とされていたためでしょう。
この日から正月飾りを飾って良いとされており、門松にするための松や、おせちを調理するための薪を山へ伐採しに行く習慣もあったとか。
煤払いはただの掃除ではなく、一種の神事でもありました。
家の中に溜まった煤や埃を払うと同時に、目には見えない邪気を祓ったうえで年神様をお迎えする。そういう行事だったんですね。
余談ですが、江戸時代は煤払いが終わると胴上げをするのが慣例だったそうです。周囲をピカピカに磨き上げた達成感を味わいつつ、なんだかおめでたい感じで一日を終えられそうな気がしますね。
作中に登場した「煤払い」は荒魂の発した軽口にすぎず、張り詰めていた雰囲気を解きほぐすために用いた言い回しでした。
とはいえ、そのシーンでの刻雨が韵貞の穢れを身に受けており、自ら祟りに染まりかけていたことを思うと、「祓いの儀式の道具(使用済み)」に例えられるのは、実はブラックジョークもいいとこ…だったりします。
荒魂は元々、自分に関する笑えない冗談を平気で口にするタイプなので、もはや身内と思われている刻雨がブラックジョークの餌食になるのは、まあさもありなんという感じですね。
『松の木』の巻
先述の『煤払い』にて少し触れましたが、12月13日に「正月事始め」を迎えた後は、正月飾りを飾って良いとされています。
25日まではクリスマス飾りの方をよく見かけるかと思いますが、その後ちらほらと町に現れるのが、門松です。
お正月シーズンのことも「松の内」なんて言ったりしますし、「松竹梅といえばなんとなくおめでたい」というイメージを持っておられる方も多いのではないでしょうか。
作中でも、そんな「松」を描写したシーンがいくつかありました。
松は何故めでたい?
松は古来より、神の憑り代、神が宿る木として考えられてきました。
これは一年中緑の葉をつける常緑樹であることや、樹齢が数千年と長いものもあることから、不老長寿や永遠の命をと結びつけられたことに由来する、という説があるようです。
寒い冬でも色褪せず緑を保つ強さがあり、雪の重さにも耐えることから、「千代木」などという別名もあるとか。
防風林としての松
先述のように、松は力強さの象徴でした。
そして人々は、そんな松を「人々を守る壁」として使うことを思いつきます。
沿岸部では海水や砂丘の砂が風に吹き上げられることがありますが、一般的な植物は、塩水や塩が葉につくと枯れてしまいます。畑や集落が、砂で埋め尽くされてしまうようなこともあります。
そこで人々は海からの風を防ぐべく、強い樹木を植林して風を防ぐことにしました。
塩にも負けず、砂浜でも育つ樹木ということで白羽の矢が立ったのが松(クロマツ)です。
松の葉は細いため、風で煽られにくく、風の力を弱めるのにも有効でした。
とはいえ、そんな松ですら、小さな苗木を沿岸部に根付かせるのは難しく、人々は防風垣を作ったり、様々な工夫を余儀なくされたようです。
そんな歴史をもとに、「港町の人々と松姫」のエピソードを組み立てました。
ただ、松の生育速度はあまり早くなく、「十年ほど前に亡くなった松姫が根付かせきれなかった松が、既に防風林として機能している」というのは、ちょっと描写が甘かったな~~~と反省しています…。
余談ですが、クロマツは平地でも防風などに一役買っているようです。参考:築地松
掛詞にも使われる松
たち別れ いなばの山の 峰に生ふる
まつとし聞かば 今帰り来む
上に引用したのは、古今集にある在原行平が詠んだ和歌です。
百人一首にもあるので、学校で暗記させられたな〜なんていう方もいらっしゃるかもしれません。
現代語訳:
あなたとお別れして、因幡の国へ参ります。
その地にあるいなばの山の峰に生える松のように、
あなたが待っていると聞いたなら、今すぐにでも帰って来ましょう。
松のように…待つ?
そう、掛詞というやつです。
皆さん、古典の授業で習ったことがあるのではないでしょうか。
修辞法の一つで、ひとつの言葉にふたつ以上の意味を持たせたもののことです。
「松」は上記のように有名な和歌にも度々登場しますが、それは大抵、「松」の描写に重ねて誰かを「待つ」人の姿を重ねているものだったりします。
そも、この「松」という木の名も、先述の「常緑樹である→不老長寿→神が宿る」という考えから、神がその木に宿るのを「待つ」からこそ「松」となのだという説もあるようです。
あるいは、神が宿る木を「祭る」から松なのだとも。
実は一作品目のラスト付近、神鹿は松の木の下で刻雨を迎えています。
これは、「この時点で既に神鹿は後継を疎んでおらず、ただ時が来るのを待っていた」ことの暗喩のつもりで描写しました。
港の松林で刻雨を待っていた竜胆/結唄の姿にも、これと同じ暗喩を用いています。
ちなみに、これも余談ですが…。
上に引用した和歌は、人々に広く知られるようになってから、「別れた人や動物が戻ってくるように願掛けをする」時のおまじないの文言として使われたりもしたそうですよ。
『和御魂』の巻
今回は神道における、「神が併せ持つふたつの側面」のお話です。
古来、日本の人々は、自分たちの暮らす土地に根付いた「自然」を「神」としてきました。
その対象は太陽であったり、山であったり、大岩であったり、川であったり……。
それらの信仰は、仏教を始めとした他国の文化が伝わってからも絶えることなく、ときに神から仏へ名を変えたりしながらも、脈々と息づいているのかな、と肌感覚として実感しています。
こうした『八百万の神々』にまつわるエピソードを見ていて感じるのは、神も万能ではないということ。
失敗もするし間違いも犯す。
これは例えば、常であれば田畑に恵みをもたらす川であっても、ひとたび荒れれば人も町も押し流します。
そういう二面性が、そのまま神格化されているからであろうと思われます。
神道では、この二面性を「荒御魂(荒魂)・和御魂(和魂)」とし、神の霊魂にはこのふたつの側面があるとしているそうです。
荒御魂は神の荒々しい側面とされ、勇猛さの一方、災いや祟りを引き起こすこともある霊魂。
和御魂は神の優しく平和的な側面とされ、幸運・収穫などを司る幸御魂と、知識・才略などを司る奇御魂に分けられるといいます。
荒御魂と和御魂は、同一の神であっても別の神に見えるほどそれぞれに強い個性があり、神によっては、本体(?)とは別個の名を与えられることもあるそうです。
更に、荒御魂は破壊と創造…的な、新しい事象や物体を生み出すエネルギーを内包しているともされることから、新御魂(新魂)にも通じるとか。
もうおわかりでしょうが、荒魂の名は、この考え方をモチーフにして名付けました。
不完全な神格を得てこの世に生まれた刻雨が、「封じられ・欠けていた祟りの側面」に代わる荒御魂を獲得し、一柱の神として完成する…。
そんな構図にしようと…、思ってたんですね…、牙卵無印のプロットを組んでいた時点では……。笑
実際は、奥台・御晴野編を経てなおふたりあわせて一神前(一人前)というところにはまだ遠く及ばない地点にいる気がしますが、スタート地点には立った感じかな?なんて思っています。
作中で「荒魂」の名を付けた刻雨は、「荒魂/和魂」という言葉は知らない(世界観として存在しない)という設定です。
知っていて名付けたとなると、色々と問題が…あるなと思って…。
あくまでも、「新玉」の名から音を借りた、ということにしておこうと思います。
その代わり作中では、神の持つ二面性を「陽の気」「陰の気」というように書き表しました。
神鹿が言ってたやつですね。
ところでこの二面性、何かを思い出しませんか?
私は先述の『ラノベ夢幻能』の項目に記した、能と狂言で演じ分ける二面性にも、これとかなり近しいものを感じています。
『名付け』の巻
「理解する」という意味で「わかる」という言葉を用いる時、みなさんはどんな漢字を用いますか?
「解る」「判る」などは、文字からも「理解」「判別」という意味を見て取れます。
では、「分かる」は?
「わかる」を何故「分かる」と書くのか、定説などがあるのかどうか、きちんと調べたことはないのですが、私はこういうことだと思っています。
「分かる」=「わからないその他諸々と区分する行為」
私達はあるひとつを理解する際、その他諸々と切り離したそれを認識することで「分かる」のです。
そして私は、ある者が何かに名をつける行為というものも、その何かをそれ以外と切り離し、それ単体の形を「見定める」=「分かる」行為であると考えています。
だからこそ名付けのシーンが…、めっちゃ…、好きなんですよねっっっ…!!!!!(力強く)
──あたしは妖狐だけど、美尾になったら、妖狐じゃなくなる?
──妖狐であることに変わりはねえけど、その名を知る者にとっては、美尾って名前の特別な妖狐になる。
特別といえば聞こえは良いけれども、この瞬間荒魂は、美尾を他の「名のない清梯山の妖狐達」から切り離してしまったのだろうなあと思っています。
清梯山の銀狐に竜胆と名付けた、天千代も同じく。
とはいえ、名で呼ぶことを天千代にだけ許していたであろう竜胆と違って、美尾はあちこちで無邪気に「美尾って呼んで!」を主張する気がするので…、
荒魂も、特別なこととすら思わずに竜胆のこと竜胆姫って呼ぶので…、
もしかしたら奥台・御晴野編以降、清梯山では空前の名付けブームが到来したりするのでは?なんていう平和な想像をしていたりもします。
刻雨
先述の『和御魂』の巻に書きましたが、「荒魂」の名前には作中では明かされないメタ的な意味がありました。
実は刻雨の名前にも、同じくメタ的な意味があります。
刻雨の名前というか…、正確に言うとあだ名の方ですが…。
本作のタイトル、『のっぺらぼうと天宿りの牙卵』には実はいくつか仕掛けがありますが、そのうちのひとつが、「あまやどり」を「雨宿り」ではなく「天宿り」としたところにあります。
主人公の刻雨の幼名は「天千代」。
神の血を引きながら、神になれず人になることを願った青年に付けられた名が「刻雨」です。
──天千代と言ったわね。おまえ、雨は好き? わたくしは好きなの。天から地へ、救いの糸のように降る雨が。
──おまえがそれを望むなら、おまえは人にお成りなさい。天より降る雨に乗って。
この「雨」という字、奥台・御晴野編では、「天千代を助けた雪鳴の名から一文字もらった」という設定も加わりました。
ですが設定として重要なのは、「天」が転じて「雨」になったということの方だったりします。
「天」=「雨」
では「刻」とは何か。
作中ではこの文字を「とき」と読ませていますので、素直に「刻雨」=「雨がふる時」=「天ではなく地に足をつけて生きていくことを意味する名」という解釈もできるなと思っています。
でも、あくまでも「時雨」ではない。
(まあキャラ造形的に「しぐれ」って感じでもない)
実のところ私としては、「刻まれた天」「傷を負った天」という意味を意識して付けた名前でした。
で、ここで活きてくるのが「ハルサメ」です。
今までに何度か、荒魂がつけた「ハルサメ」というあだ名は、はたして食べ物のハルサメなのか、それとも雨の表現としての「春雨」なのかと聞かれたことがあります。
まあ荒魂の意図としては…、食べ物のハルサメのつもりで付けたあだ名ですね。
完全に余談なんですけど、荒魂は「仲良くしたほうが良さそうだけどちょっととっつきにくい」と思っている相手に、相手が突っ込まざるを得ないようなビミョウなあだ名をつける、という設定があり…。
萬景にいた頃の荒魂は、実のところ法師と名乗る相手全般に対して良い印象を持っていないので、元々茶化す意味でハルサメのあだ名をつけています。
「あだ名で茶化しているうちに、こっちの手のひらに乗ってきてくれねえかな〜」という打算があるわけです。
そういう思惑で荒魂は、面白おかしく茶化すために、「御晴野」の「晴」の音を持ってきた。
刻雨の人生について回る、「刻」の字をまるっと無視して。
──大体、ハルサメ君って誰のことです。
──そりゃ、おまえの事だよ。御晴野刻雨だろ? 晴れてるんだか、雨なんだか、よくわからねえ名前だよな。
刻まれ、ぼたりぼたりと地に何かを降らせていた天を、この時点でばっさりと、「晴れてるんだか、雨なんだか、よくわからねえ」ものにしてしまった。
そういう仕掛けがやりたくて付けた名と、あだ名だったのでした。
「荒魂」の名付けも、「ハルサメ」の名付けも、実のところこんな意味を考えていました。
でも彼ら自身はその事に気づいていない。
気づかないままとっくに神格を与えていたり、とっくに傷を晴らしていたり、そういう関係性を、本編ではまた別の角度から描いたつもりです。
なお、これは蛇足ですが…。
この作品ははじめから「もりもり食べる二人組の話」にするつもりだったので、実は全員食べ物っぽいあだ名を付けるという案もありました。
白玉とか。「新玉」も「新玉ねぎ」っぽかったりとか。
でもネタとしてつまらなかったのでボツにしました。
作品タイトルの略称も、「とりがら(鶏ガラ)」にするつもりだった。無理がある。ボツにしてよかった。
奥台・御晴野編で、荒魂が美尾をからかって、「み」で始まる食べ物の名前を呼びまくる、というくだりは、その名残だったりします。
(あれ考えるの大変だった〜〜〜)
竜胆
既にお気づきの方もいらっしゃるようなのですが、竜胆の花言葉は「悲しんでいるあなたが好き」です。
か、か、かかか…、悲しんでいる、あなたが好き…!?!?!?!?
ふだんあんまり花言葉などに興味がないタイプなのですけど、このエモすぎる花言葉を知って以来ずっと、いつか使いたいと思い続けていました。
いつか使いたい。何かの折に使いたい、いつだ。今だ。今がその時だ!!!
ということで彼女の名を「竜胆」にしたわけで。刻雨と竜胆の関係性は、完全にこの花言葉から膨らませたものになっています。
悪くいえば、お互いの悲しみに付け入るような。
良く言えば、お互いの悲しみに寄り添うように。
そういう幼少期になりました。
リンドウの花には、他にも「あなたの悲しみに寄り添う」「勝利」「満ちた自信」などの花言葉もあるそうです。
なお、刻雨が彼女に「竜胆」と名付けた作中の表向きの理由は、「リンドウの花のように群れない美しい佇まいを見たから」というものの他に、実はものすごくしょうもない理由があるのですが、それはまた別の機会に…。
新玉
上に、「新玉ねぎ」っぽいとか書いてしまったので、一応補足を…。
「新玉」という言葉には元々、「新しい年」とか、「掘り出されたまま、まだ磨かれていない玉」「真価を発揮していない素質のある人」という意味もあります。
最終的に「荒魂」に繋げるための名前ではありましたが、これはこれで、その名のとおりであると良いね…。と思ったりします。
『渾天説』の巻
──仁駱山に訪れた、猛り狂う暴風雨。
空は妖しく紫色に淀んで光り、渾天の隅々からかき集めたかのような、鋭い風が吹き荒れた。
天地を覆すかのごとくに地響きが轟き、地に立つ全てを打ち倒さんとするように、大粒の雨が叩きつけた。
天千代が体験した、仁駱の山の異変に関する描写です。
ここで私は、何気なく「渾天」という単語を用いましたが、これには実はちょっとした意味があります。
「渾天」とは、簡単に言えば「天空のすべて」のこと。
このシーンにおいて、仁駱山および飛鳥井の屋敷というのは天千代にとっての「世界のすべて」であり、その土地で起きた異変の描写をするべく、どんな言葉を用いればいいだろうかと唸っていた頃に、あれこれ調べて辿り着いたのが、この「渾天」という言葉でした。
古代中国天文学における宇宙構造論の一つに、「渾天説」というものがあります。
今のように、地球という星の外には宇宙空間が広がっているとは知られていなかった頃の考え方です。
渾天説では、天は鶏の卵殻のように球形で、地は卵黄のようにその内部に位置するとされています。
世界は巨大な卵の形をしていて、私達はその中にある卵黄で暮らしているのだと。そういう考え方があったんですね。
なお、卵黄とはいえ地球が丸いという発想はまだなかったようで、天の半分は地上を覆い、半分は地下を囲んでいるとされていたようです。
だからこそ、見えない星があるのだという考え方だったのだとか。
食って喰ってで進むこの物語の中で、真っ先に喰われるのが「牙卵」。
彼らにとってこんなにもふさわしい世界観があるだろうか。そう考えて採用したのが「渾天」という言葉でした。
さらっと読み飛ばしちゃうようなところだと思うんだけど……、笑
こういう何気ないところに思いっきりこだわりを詰められるのが、創作の醍醐味だよなあ、と私は思っています。
『形代』の巻
形代
形代とは本来、呪術を行う目的で人等を模してつくる道具のことを指します。
呪術、というとおどろおどろしい呪いなどを思い浮かべるかもしれませんが、形代は本来、凶用と善用どちらの目的にも用いられます。
いわゆる丑の刻参りの呪いの藁人形なども形代ですが、雛人形や五月人形も、もとは形代の一種です。
祭事にも取り入れられており、例えば大祓では、天皇等が人形代に一撫一吻し、罪穢や病気を人形代に移したうえで、それを河川に流します。
雛人形や五月人形も本来は毎年流すものだったそうで、紙や土製で人形を作り、川に流していたようです。(現代にも残る例:流しびな)
人の穢れや病を託すためのもの=形代。
そしてこの「穢れ」や「病」というものは、古くは悪霊や疫病神であるとされ、神霊的なものと考えられていました。
そういう意味で形代とは、広義では「人為的に加工された神霊の憑依体・依代」でもあるわけです。
そんなところから、物語の中の「神の祟りをその身に請け負う能力、形代」の設定を練り上げました。
飛鳥井と形代の力
──形代は加護の力などではない。それは我が飛鳥井家の人間が、代々受け継いできた我らの力。
──皇の血族のうちでも、最も身を尽くし血を流し続けてきたのが我が一門。だが穢れに触れる忌むべき能力を持つが故に、飛鳥井は代々不当な扱いを受けてきた。
今回、本編からは読み取れない裏設定をガンガン出しますので、そういうものが苦手な方はご注意ください。
ここから先は、物語中の飛鳥井の降智の話。
本編はあくまでも刻雨視点なので、降智のことは終始一貫して悪役風に描写しました。
でももし牙卵のスピンオフを書くとしたら、彼、現時点で最も主役になりうるポテンシャルを秘めた男だと思うんですよね……。
まず大前提として彼の属する飛鳥井の一門は、神とも等しい山護の力に作用する、皇の一族の血を引いている。
しかしながら飛鳥井が行使しうる力は、「己の身を犠牲にして他者の穢れを祓う(請け負う)」というもの。
外部には秘匿されていた能力とはいえ、これは皇の一族の中では周知の力であっただろうと思われます。
となると、恐らく彼の身近な肉親にも、形代の力を持って生まれ、他人の身代わりになって命を落としたケースがあったと思うんですよね。
降智の親兄弟もそうして死んでいるかもしれないし、子もそうなるかもしれない。
その上で、降智自身は形代の力を持っていなかったんじゃなかろうか。
一門の中に、形代の力を持って生まれる者と持たずに生まれる者がいるなら、持たない者が家を治めたほうが冷静な判断を下せるように思うし、家の存続もし易いのではないかと思うので。
つまり彼は、飛鳥井の一門に生まれながら形代の力を継いでおらず、それ故に当主となった。
そして飛鳥井の境遇を憂いていた彼は、一門の待遇改善のため、なんとしてでも吉野西鶴との跡目争いに勝ち、帝の座を簒奪せねばならなかった。
だからこそ禁を犯して、祀るべき山護を討った。
それでも山護の力を得ることはできず、想定外の結果として、妹の胎に山護の子が宿り、生まれでた。
生まれた子供は人ならざる姿をしてはいたものの、行使しうる力は結局、飛鳥井の一門を苦しめてきた形代の力だけだった。
しかも、天千代は人外の頑丈さだけは持ち合わせているので、形代の力を用いても死にはしないんですよね。
今までに形代の力を用いて死んでいった肉親達は一体何だったのかと、思ってしまいますよね……。
降智は結局、跡目争いに勝てなかったどころか、山護を討った咎で一門を破滅に追い込んでいます。
罪人として流刑に処された飛鳥井の人々は、今後も必要に応じて形代の力の行使を強いられるだろうと思われます。
皇に連なる飛鳥井の人間として扱われていた頃より、相当厳しい状況にあるのは間違い有りません。
奥台・御晴野編では、だからこそ一門の再起のため、現帝の要求に応じざるを得なかったんだろうなと。
そんなこんなで暗躍しているところへ、行方不明になっていた天千代が突然何喰わぬ顔で現れたら、しかもそこそこ健やかに育った感じを出してたら、そりゃ情緒ぐちゃぐちゃになるよ。(?)
期待された力を持って生まれなかった天千代を責める言葉の中には、降智がかつて自分自身に向けた言葉もあったんじゃないかなと、そんなことを思いながら執筆しました。